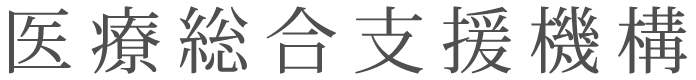「がん治療を受けたい。でも⋯」|お金の不安にゆれるあなたへ
「治療を受けたいけど、これからいくらかかるんだろう⋯」
がんと診断されたとき、まず頭に浮かぶのは“命”のこと。
そして次は“お金”のことではないでしょうか。
治療費で家計が大きく揺らいだら、これからの生活費は?子どもの教育費は?ー
「お金のことが頭から離れなかった」という声も多く聞かれます。
実際に、お金の不安から治療を迷ったり、先延ばしにしてしまう人も少なくありません。
けれど実は、そうした不安をやわらげる制度が国によって用意されています。
『高額療養費制度』はそのひとつ。
これを知っておくだけでもお金の不安はぐっと軽くなるかもしれません。
この記事では、高額療養費制度が生まれた背景と、どのように患者さんを支えているのかをお伝えします。
高額療養費制度が生まれた背景とその仕組
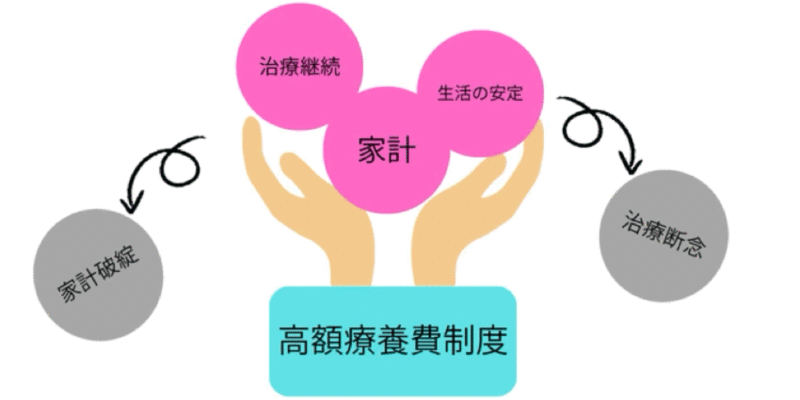
「医療費が払えないから治療を諦める」ーそんな時代があった
かつての日本では、全国民が公的医療保険に加入できるようになったものの、高額な医療費には自己負担額の上限がなかったため、負担がどこまでも膨らむ状況でした。その結果、大きな社会問題が生じました。
- ✕ 重い病気や長期入院では医療費支出が非常に大きく家計が破綻することがあった。
- ✕ 支払い困難となり、治療の中断をせざるを得ない患者も少なくなかった。
- ✕ 低所得の世帯ほど受診が困難となり「医療の公平性」が保たれなくなった。
このような不公平や経済的困窮をなくすため、1973年に国によって創設されたのが『高額療養費制度』。
この制度の導入によって、患者さんの経済的負担は大きく軽減されました。
- ・ 自己負担額に上限が設けられ、家計破綻のリスクが軽減された。
- ・ 長期の治療が必要な患者では、さらに自己負担が軽くなる工夫がされている。
- ・ 経済的理由により治療を諦めることが減り「医療の公平性」が向上。
この制度は、単なる経済支援ではありません。
「誰もが必要な治療を受けられるように」と生まれた、“治療をあきらめないための仕組み”なのです。
『高額療養費制度』って、どんな仕組み?
医療機関にかかった場合、窓口で保険証を提示すれば支払う医療費は総額の1〜3割で、残りは公的医療保険からの給付を受けられるため支払う必要がありません。
しかし重い病気や長期入院になった場合、公的医療保険制度の利用で自己負担額は1~3割でも、そもそも医療費の総額が大きいために高額の医療費を請求される可能性があります。
しかし、高額療養費制度を利用すれば医療費の負担を軽減することが可能です。
高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、1か月(1日〜末日)の間に一定の上限額を超えると、超えた分の金額が加入している公的医療保険から支給される制度なのです。この上限額は年齢や所得によって変わります。
『限度額適用認定証』があれば立て替えも不要
高額療養費制度は、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される仕組みなので、一度窓口で高額の医療費を支払う必要があります。さらに、払い戻されるまでに3ヶ月ほどかかります。
しかし、あらかじめ支払う医療費が自己負担の上限額を超えることが見込まれる場合は、『限度額適用認定証』を取得することで窓口での支払いは限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証は、加入している医療保険の運営者に申請することで取得できます。
さらに金銭的負担が軽くなる仕組みも
長期間治療が続く人に向けた『多数回該当』という制度もあります。
直近12か月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられる特例制度です。
また、大手企業などの健康保険組合では独自の『付加給付』を設けている場合があり、さらに負担が軽減されることもあります。なお、国民健康保険や協会けんぽではこの制度はありません。
制度には限界があるけれど、それでも“ある”という安心
高額療養費制度は非常に頼りになる制度ですが、すべての費用が対象になるわけではありません。
入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療の費用は制度の対象外です。
また、月をまたいで治療が続く場合はそれぞれの月で限度額が発生するため、時期によっては想定よりも出費がかさむ場合もあります。
それでも、「制度があるから治療を受けられる」と感じる人がいることも事実。
制度の存在が、患者さんの背中をそっと支えてくれているのです。
42歳・佐藤さんの話ー「制度を知っただけで気持ちが変わった」

乳がんと診断されたとき、命の次に気になるのはお金のことだった
42歳の佐藤さんは、夫と2人の子どもと暮らす共働きの母親です。
健診で乳がんの疑いが見つかり、精密検査の結果「初期の乳がん」と診断されました。
突然の診断に驚き、気持ちが追いつかないまま主治医の話を聞いていた佐藤さん。
手術・抗がん剤治療・放射線治療など、複数の治療を組み合わせる必要があることを知り、命への不安とともに頭をよぎったのは「いくらかかるの?」という金銭面のことでした。
共働きでやっと成り立っている生活。子どもの教育費、住宅ローン、生活費⋯。
「私が働けなくなったうえに、高額な治療費までかかったら⋯」と、不安に押しつぶされそうになっていました。
ネットで見つけた「高額療養費制度」の存在が不安を軽くした
そんなときに、インターネットで偶然見つけたのが「高額療養費制度」でした。
佐藤さんは年収約400万円の会社員。
このケースでは、もし1ヶ月の医療費が100万円かかった場合、窓口での支払は3割負担で30万円となります。そして高額療養費制度を利用することで、21万円が支給されるので、佐藤さんの実際の負担額は約9万円となります。
さらに限度額適用認定証を取得しておけば、窓口での立て替えも不要です。
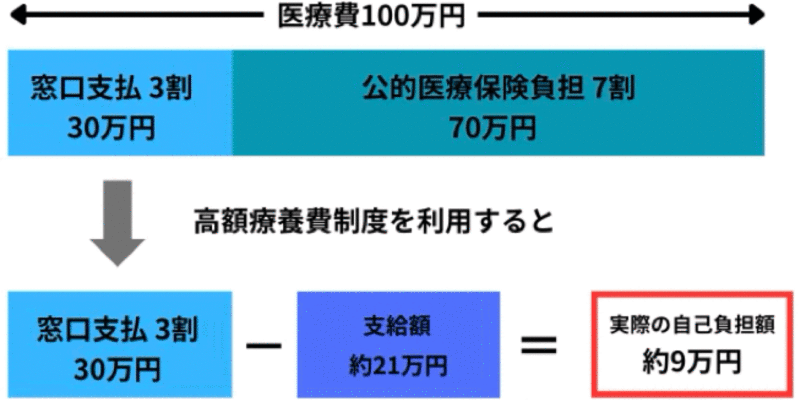
治療は数ヶ月続くと主治医から説明されていましたが、多数回該当が適用されれば4ヶ月目以降は自己負担の上限額が44,400円まで下がります。
佐藤さんは高額療養費制度の存在を知ったおかげで、少し安心することができました。さらに治療で通うことになった医療機関の相談窓口で、お金のことや生活面の相談ができたことも不安の軽減につながりました。
医療費の見通しが立ち、「払えないかも」という不安が「これなら払えるかもしれない」と思えたことで、佐藤さんの表情にも少しずつ笑顔が戻ってきたのです。
まとめ:“困ってから”ではなく“困らないように”備える

医療費の不安から一人で悩んでいる患者さんは少なくありません。
佐藤さんも最初は不安でいっぱいでした。
しかし『高額療養費制度』という存在を知り、相談窓口で具体的な情報を得ることで治療に専念することができました。
お金の不安を軽減し、安心して治療と日常生活を継続できる環境を整えることはとても重要です。そのためには制度や支援内容を「知る」ことがまず第一歩。
- ・ 医療機関の相談窓口を利用する
- ・ 自治体や公的医療保険の窓口での相談
- ・ インターネットを利用し公的機関サイトで情報と相談先を探す
(厚生労働省、がん情報サービス、主要病院の公式サイトなど)
これらの窓口や団体を利用し、早めに相談することがおすすめです。
「知っていれば、もっと早く安心できた」
その言葉が現実にならないように、まずは相談してみませんか。
あなたの不安を減らす第一歩になるかもしれません。
(前田 真彩)
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ
[ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html ] - がん情報サービス
[ https://ganjoho.jp/public/index.html ]