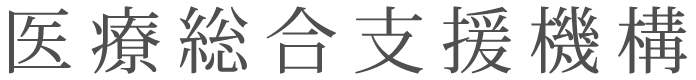「がん治療が怖い…」そんなあなたへ|不安をやわらげるために知ってほしいこと
がんと診断されたとき、最初に浮かぶのは「怖い」という気持ち。
それは、誰にとっても自然な感情です。
ー家族が抗がん剤の副作用で苦しむ姿を見てきた
ーがん治療による痛みや身体の負担が心配
ーネットでネガティブな情報を目にしてしまった
不安を感じる理由は、身の回りにたくさんあります。
だからこそ、「怖い」と思うのはあなただけではありません。
この記事では、がん治療への不安を少しでも軽くするために、「治療とどう向き合っていけばいいのか」を一緒に考えていきます。
「治療が怖い」その気持ちは自然な反応です

「治療が怖い」「副作用が不安」という気持ちになるのは、とても自然なことです。
がん治療には、抗がん剤の副作用や放射線治療の身体への負担など、心配になる要素がたくさんあります。
副作用など、身体への負担が怖い
がん治療には、抗がん剤や放射線治療など、身体への負担が大きいものがあります。
副作用としてよく知られているのは、吐き気や脱毛、だるさ、食欲不振などです。
こうした副作用の話を聞くだけで、「自分も同じように苦しむのでは?」と不安になるのは当然のことです。
家族のがん経験がトラウマになっている
家族や友人など、身近な人ががんでつらい思いをしている姿を見たことがある人は、より一層その恐怖が強くなる傾向があります。
「またあの光景を繰り返したくない」「家族にも迷惑をかけたくない」という思いが、治療への不安を大きくしてしまうのです。
ネットやSNSでのネガティブな情報に影響されてしまう
インターネットやSNSでは、「抗がん剤は効かない」「標準治療は意味がない」といったネガティブな情報が目につきやすいものです。
こうした情報は正しいとは限りませんが、心が不安定なときにはつい信じたくなってしまうこともあります。
「怖い」という気持ちは自然なものです。
では、ほんとうに治療は怖いものなのでしょうか?
また、どんな治療が選択肢としてあるのでしょうか?
まずは、「標準治療」について知っておきましょう。
標準治療は「最良」の治療
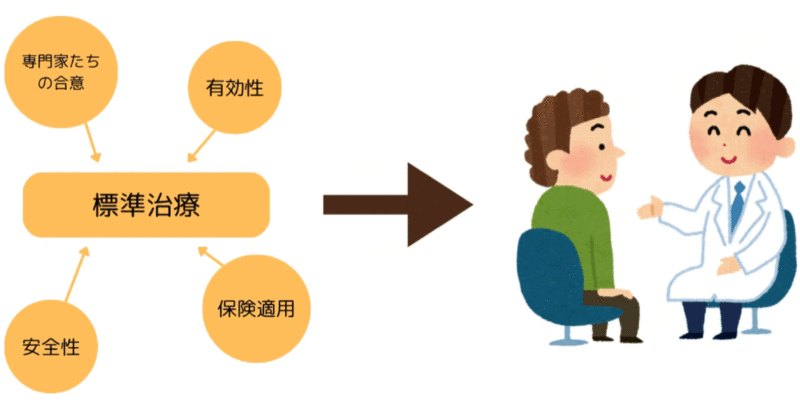
がん治療について調べていると、「標準治療」という言葉をよく目にします。
標準治療は、科学的な根拠に基づき、多くの患者さんへの効果や副作用、安全性がしっかり確認された治療法です。国が定めた診療ガイドラインに沿って行われ、ほとんどの病院で保険適用として受けることができます。
「標準」という言葉から「普通の治療」と思われがちですが、決して妥協した治療ではありません。
「多くの人にとって、今できる最良の治療」が標準治療なのです。
ただし、「標準治療がすべての人にとってベストな選択か?」というと、それはまた別の話です。
「最良」の治療がみんなのベストとは限らない

標準治療が「最良」の治療法であることは間違いありません。
ただし、この「最良」は、あくまで平均的な評価であって、すべての人にとって必ずしもベストな、「最適な治療」とは限らないのです。
たとえば抗がん剤治療が合わない場合もある
標準治療である抗がん剤治療は、科学的な根拠に基づき「最も効果がある」とされています。
しかし、副作用が強く出てしまい、毎日の生活に大きな支障が出る場合もあります。
その人の状況や希望によって「最適」は変わる
高齢の患者さんの場合、積極的な標準治療よりも「自宅で穏やかに過ごす」選択肢が「最適」になることがあります。それは、治療の効果だけでなく、生活環境や価値観、家族との時間を大切にする気持ちも大事だからです。
「最適」とは、その人にとって最もふさわしく、納得できる治療のかたちを意味します。年齢や体力、生活環境、価値観、家族の状況、そして「これからどう生きたいか」という希望ーこれらをすべて考慮したうえで、治療は決めていくものです。
一人ひとりに向き合った「最適」な治療とは
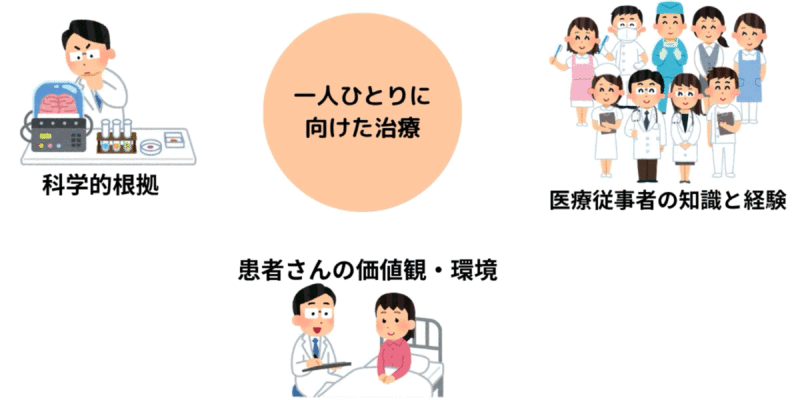
治療はただ標準治療を当てはめるだけでなく、一人ひとりに合った「最適な治療」を考えます。
「最適な治療」を決める流れ
具体的には、次のような流れで治療方針が決まっていきます。
- 1. 目の前の患者さんの状況から疑問を明確にする
- 2. 疑問をもとに情報を集める
- 3. 集めた情報をしっかり吟味す
- 4. 吟味した情報を、その患者さんに合う形で適用する
そして、1.〜4.の実践をふり返り、次にどう活かすかを考えます。
治療法は「これが正解!」と決めつけるのではなく、その患者さんの体や心の状態、生活環境に合わせて柔軟に考えていく必要があります。
治療を決めるときに大切な4つのポイント
1. 科学的根拠(エビデンス)
- ・ 多くの人を対象に、治療の効果や安全性を調べた「臨床研究」の結果
- ・ 標準治療も、エビデンスに基づいて選ばれた治療法のひとつ
2. 患者さんの病状や周囲の環境
- ・ 年齢や体力、家族構成や経済的状況など
- ・ 通院先の病院へのアクセスのしやすさ
3. 患者さんの意向や価値観
- ・ 副作用やリスクをどれくらい受け入れられるか
- ・ 「自分で決めたい」「家族と相談しながら決めたい」という意思決定のスタイル
4. 医療従事者の臨床経験
- ・ これまでに見てきた患者さんの症例や経験から得た「現場感覚」
- ・ ガイドラインを「ただ押し付ける」のではなく、患者さんの状況に合わせて調整する力
このように、科学的根拠(エビデンス)が大事なのは間違いありませんが、医療はそれを「押し付ける」ものではありません。
患者さんの価値観や状況を大切にしながら、一緒に治療を考えていくことが、治療で大切にしたい考え方です。
怖さを減らすためにできること

「治療が怖い」「副作用が心配」「どうなってしまうのか分からない」
ーそんな不安な気持ちは、あなただけのものではありません。
実際に、がんと向き合う多くの方が同じような思いを抱えています。
でも、怖い気持ちは完全に消せなくても、少しでも不安を軽くするためにできることはあります。
正しい情報を知る
怖さの多くは、「分からない」ことから生まれます。
ネットの情報には誤解を招くものや、極端な意見も多いので、信頼できる情報源を選ぶことが大切です。
たとえば、がん専門病院の公式サイトや「がん情報サービス」などの公的機関は、科学的根拠に基づいた最新の情報をわかりやすくまとめています。
「分からないこと」をそのままにせず、医師や看護師に質問してみるのも大切な一歩です。
医療従事者に自分の気持ちを話してみる
「治療が怖い」「副作用が心配」といった気持ちは、医療者に話しても大丈夫。
むしろ、患者さんの気持ちを聞くことは医療従事者にとって大事な仕事のひとつです。
治療法のメリットやデメリット、他に選べる選択肢があるかどうかも含めて、一緒に考えていけます。
同じ経験をもつ人と繋がる
「私だけじゃない」と思えることが、怖さを軽くする力になります。
同じようにがん治療を受けた人の体験談を読む、患者会やオンラインコミュニティに参加してみるなど、「話せる場所」を見つけるのも方法のひとつです。
不安や疑問を共有できる仲間がいることで、少しずつ心が軽くなるはずです。
怖い気持ちはあっていいし、ゼロにする必要もありません。
でも、できることから少しずつ取り組んでいくことで、「治療と向き合える心の準備」が整っていきます。
まとめ:治療と向き合う患者さんへ伝えたいこと

がんと診断され、「怖い」という気持ちを抱えるのは、決して特別なことではありません。
家族の経験を思い出したり、副作用の話に不安を感じたり、迷う気持ちが出てくるのは当然のことです。
でも、がん治療は「押し付けられるもの」ではなく、患者さん自身が納得できる形で一緒に考えていけるものです。
科学的根拠に基づく治療の選択肢があること、そしてその中で「あなたにとっての最適な治療」を選ぶ余地があることを、どうか覚えておいてください。
(前田 真彩)
- 厚生労働省 eJIM「統合医療」情報発信サイト『「根拠に基づく医療(EBM)」を理解しよう』
[ https://www.ejim.mhlw.go.jp/public/hint2/c03.html ] - 日本内科学会『Evidence-based medicine:診療現場でのプロブレムの解決法』
[ https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/106/12/106_2545/_pdf/-char/ja ] - 国立がん研究センター がん情報サービス
[ https://ganjoho.jp/public/index.html ] - ドクタービジョン『いま改めて考える「EBMとは」―医師がおさえておきたい、全体像や課題』
[ https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/knowledge/ebm.php ]