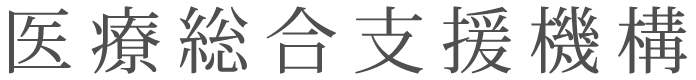『いびき』『昼間の眠気』『朝の疲れ』ー放置は危険!睡眠時無呼吸症候群の症状と受診の目安
最近、朝起きても疲れが取れない、日中に強い眠気を感じる、家族からいびきがうるさいと指摘されるといった症状はありませんか?これらの症状は、睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)のサインかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする疾患で、成人に多いですが特に働き盛りの中年層に多く見られます。単なる「いびき」や「疲労」と軽視されがちですが、放置すると高血圧や心疾患、脳血管障害などの深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
また、昼間の眠気からくる居眠り運転や仕事の能率低下など、日常生活にも大きな影響を与えます。
本記事では、睡眠時無呼吸症候群の基本的な知識から症状の見極め方、診断・治療法まで、詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせながら、適切な医療機関への受診を検討する際の参考にしてください。
睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が停止する「無呼吸」や呼吸が浅くなる「低呼吸」を繰り返す疾患です。医学的には、10秒以上の無呼吸や低呼吸が1時間あたり5回以上起こると診断されます。
睡眠時無呼吸症候群の分類
睡眠時無呼吸症候群は、発症のメカニズムによって以下の3 つのタイプに分類されます。
| 閉塞性睡眠時 無呼吸症候群 (OSA) |
・ 全体の大部分を占める最も一般的なタイプ ・ 上気道(のど)の物理的な閉塞により呼吸が阻害される ・ 肥満、加齢、顎の形態などが主な要因 |
|---|---|
| 中枢性睡眠時 無呼吸症候群 (CSA) |
・ 脳の呼吸中枢の機能異常により発生 ・ 心不全や脳血管障害に伴って生じることが多い |
| 混合性睡眠時 無呼吸症候群 |
・ 閉塞性と中枢性の両方の要素を持つ |
特に多いのは「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」で、舌やのどの筋肉が緩んで気道が塞がり、空気の通り道が一時的に閉じてしまうことが原因です。結果として呼吸が止まり、血中酸素が低下し、体は酸素不足と戦うことになります。このため夜間に深い睡眠が得られず、翌朝に疲労が残ったり、昼間の強い眠気につながったりします。
日本における睡眠時無呼吸症候群の患者数と潜在患者の多さ
日本国内では、推計940万人が睡眠時無呼吸症候群を発症しているとされますが、その多くは未受診・未診断のまま放置されていると言われています。つまり、睡眠時無呼吸症候群は「気づいていない患者が圧倒的に多い」病気といえます。
日本における睡眠時無呼吸症候群の有病率は、成人男性の約3~7%、女性の約2~5%と報告されています。特に40~50歳代の働き盛りの男性に多く見られ、肥満や飲酒習慣、喫煙などの生活習慣が発症リスクを高めることが知られています。
女性は閉経後、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、のどの筋肉がゆるみやすくなり、いびきをかきやすくなります。これが、女性が閉経後に睡眠時無呼吸症候群のリスクが上がる原因の一つと考えられています。
睡眠時無呼吸症候群はなぜ気づきにくいのか
睡眠時無呼吸症候群が自覚されにくい最大の理由は、症状が「睡眠中」に起こるためです。本人は無意識のうちに呼吸が止まっており、自覚することはほとんどできません。
「大きないびき」「息が止まっている」と気づくのは、同居している家族やパートナーからの指摘がきっかけとなることが多いのです。
また「朝起きても疲れが取れない」「日中の強い眠気」という症状は、単なる生活習慣の乱れや加齢のせいと誤解されがちです。このため、多くの人が病院を受診せず、重症化してから見つかるケースも少なくありません。
睡眠時無呼吸症候群を放置すると危険な理由

睡眠時無呼吸症候群では、睡眠中に何度も呼吸が止まるため、血液中の酸素濃度が一時的に低下します。酸素不足が繰り返されると、体は「低酸素状態から回復しよう」と交感神経を過剰に働かせ、心拍数や血圧を一時的に上昇させます。
これが毎晩続くことで、心臓や血管に負担が蓄積されるのです。
合併症のリスク
複数の研究により、睡眠時無呼吸症候群は循環器疾患や生活習慣病のリスクを高めることが示されています。
| 高血圧 | 無呼吸により血液中の酸素濃度が低下すると、交感神経が活性化し血管が収縮します。この状態が繰り返されることで高血圧が発症・悪化し、治療抵抗性高血圧の原因となることも少なくありません。 |
|---|---|
| 心疾患 (心筋梗塞・不整脈など) |
睡眠時無呼吸症候群の患者では、狭心症、心筋梗塞、心房細動などの心疾患の発症リスクが上昇すると報告されています。特に重症例では、突然死のリスクも上昇すると指摘されています。 |
| 脳卒中 | 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の発症リスクも3~4倍高くなると言われています。これは、反復する低酸素状態が脳血管に負担をかけるためです。 |
| 糖尿病 | 睡眠の質の低下や慢性的な低酸素状態は、インスリン抵抗性を増加させ、2型糖尿病の発症リスクを高めます。また、既に糖尿病を患っている場合は、血糖コントロールが困難になることがあります。 |
| 肥満 | 睡眠不足や睡眠の質の低下により、食欲調節ホルモン(レプチン、グレリン)のバランスが崩れ、過食傾向となり肥満が進行しやすくなります。 |
日中の強い眠気による事故のリスク
「昼間の強い眠気」は睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状です。
十分に睡眠をとっているつもりでも、夜間の断続的な呼吸停止で深い眠りが得られず、脳が休めていません。その結果、仕事中に集中力が続かない、会議中にうとうとしてしまうといった支障が出やすくなります。
特に問題となるのは、車の運転中の眠気です。
日本でも、睡眠時無呼吸症候群が原因と考えられる交通事故の事例が報告されています。
睡眠時無呼吸症候群の患者は、そうでない人に比べて事故のリスクが2.4倍あると言われています。
国土交通省は運転者の眠気による事故防止に関する施策を行っており、社会全体を巻き込んで対策を講じています。
生活の質(QOL)の低下
睡眠時無呼吸症候群は命に関わる病気であるだけでなく、生活の質にも大きな影響を及ぼします。
朝起きても疲労感が残り、頭が重い・集中できないといった状態が続くと、仕事や家事の効率が落ち、精神的なストレスも増加します。
さらに、熟睡感が得られないことは抑うつ傾向とも関連していると報告されています。
「ただのいびき」「ただの疲れ」と放置してしまうと、健康面だけでなく社会生活・精神面にまで悪影響を及ぼすのが睡眠時無呼吸症候群です。
睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状とサイン

睡眠時無呼吸症候群の症状は、睡眠中に現れるものと日中に現れるものがあります。これらの症状を正しく理解し、早期発見につなげることが重要です。
睡眠中の症状
- 【いびき】
- ・ 大きく、不規則ないびきが特徴的
- ・ 一時的に止まった後、再び大きないびきが始まる
- ・ 家族やパートナーに指摘されることが多い
- ・ ただし、いびきがあっても必ずしも睡眠時無呼吸症候群とは限らない
- 【呼吸の停止】
- ・ 10秒以上の呼吸停止が繰り返される
- ・ 家族が睡眠中の呼吸停止を目撃することがある
- ・ 呼吸再開時に大きな音を立てることがある
- 【睡眠中の異常な体動】
- ・ 頻繁な寝返り
- ・ 手足をバタバタと動かす
- ・ 突然身体を起こすような動作
- 【夜間頻尿】
- ・ 夜中に何度もトイレに起きる(通常2回以上)
- ・ 抗利尿ホルモンの分泌異常により尿量が増加
日中の症状
- 【昼間の眠気】
- ・ 会議中や運転中など、本来眠ってはいけない場面での強い眠気
- ・ エプワース眠気尺度(ESS)で評価されることが多い
- ・ 短時間の居眠りを頻繁に行う
- 【朝起きても疲れが取れない】
- ・ 十分な睡眠時間を取っているにも関わらず、起床時に疲労感が残る
- ・ 熟睡感がない
- ・ 頭がすっきりしない感覚
- 【集中力・記憶力の低下】
- ・ 仕事や勉強に集中できない
- ・ 物忘れが増える
- ・ 判断力の低下
- 【起床時の頭痛】
- ・ 朝起きた時の頭痛や頭重感
- ・ 通常、起床後しばらくすると改善する
身体的特徴
以下のような身体的特徴がある場合、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くなりま
- ・ BMI25以上の肥満
- ・ 首が太い(男性43cm以上、女性38cm以上)
- ・ 下顎が小さい・後退している
- ・ 舌が大きい
- ・ 扁桃腺が大きい
- ・ 鼻づまりがある
周囲からの指摘が重要な手がかりに
睡眠時無呼吸症候群の患者が自分自身で症状に気づくのは難しいケースが多く、家族やパートナーの観察が診断のきっかけになることが少なくありません。「いびきがうるさい」「呼吸が止まっていた」といった周囲からの指摘は軽視せず、医療機関に相談することが早期発見につながります。
セルフチェックでわかる睡眠時無呼吸症候群の可能性
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に症状が出るため、自分では気づきにくい病気です。そこで役立つのが、簡単な質問票やセルフチェックです。
睡眠時無呼吸症候群の可能性を簡単にチェックできる方法として、国際的に広く使用されている「STOP-BANG質問票」をご紹介します。
この質問票は医療機関でも使用されており、8つの項目で構成されています。いくつかの項目に当てはまる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるため、医療機関の受診を検討する目安となります。
ただし、セルフチェックはあくまで参考であり、確定診断には医師による検査が必要です。
STOP-BANG質問票
世界的に広く使われているスクリーニング方法のひとつです。8つの質問から構成され、いくつ当てはまるかでリスクを判定します。
| 質問内容 | 項目 |
| 大きないびきですか?(話し声よりも大きいか、あるいは閉めた扉越しに聞こえる程度) | いびき(Snoring) |
| しばしば疲労や倦怠感、昼間の眠気を感じますか? | 疲労(Tired) |
| 他の人から呼吸が睡眠中に停止しているのを指摘されましたか? | 他者からの目撃 (Observation) |
| 高血圧ですか、あるいは現在高血圧の治療を受けていますか? | 血圧 (Blood pressure) |
| BMIが35(または30)kg/m2以上ですか? | Body mass index (BMI) |
| 50歳以上ですか? | 年齢(Age) |
| 首の周囲径が40cm以上ですか? | 首周囲径 (Neck circumference) |
| 男性ですか? | 性別(Gender) |
【結果の判定】
はい = 1点、いいえ = 0点
3点以上で閉塞性睡眠時無呼吸症候群のハイリスク
※ 引用:
[ https://www.jstage.jst.go.jp/article/generalist/42/1/42_26/_pdf ]
エプワース眠気尺度(ESS)
日中の眠気の程度を評価する指標として、エプワース眠気尺度(ESS)も有用です。以下の8 つの状況で、どの程度眠くなる可能性があるかを4段階で評価します。
| うとうとする可能性は ほとんどない |
うとうとする可能性は は少しある |
うとうとする可能性は 半々くらい |
うとうとする可能性が 高い |
|
| すわって何かを読んでいるとき(新聞、雑誌、本、書 類など) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| すわってテレビを見ているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 会議、映画館、劇場などで静かに座っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 乗客として1時間続けて自動車に乗っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 午後に横になって、休息をとっているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| すわって人と話をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 昼食をとった後(飲酒なし)、静かに座っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| すわって手紙や書類などを書いているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
【結果の判定】
11点以上で過度な日中の眠気と判断します。
該当する方は、医療機関に相談することを推奨します。
※ 引用:
[ https://is.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/044110896j.pdf ]
[ https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n30/tetuzuki/ess.html ]
日本人に多いリスク因子
質問紙に加え、日本人に特徴的なリスク因子もあります。
| 肥満 | 内臓脂肪や首回りの脂肪が気道を狭める |
|---|---|
| 顎の形 | 骨格的に下顎が小さい人は気道が狭くなりやすい |
| 飲酒・喫煙習慣 | 筋肉の緊張を緩め、気道閉塞を悪化させる |
| 閉経後の女性 | 女性ホルモンの減少で睡眠時無呼吸症候群のリスクが上昇 |
こうした背景を持つ方は、より注意が必要です。
セルフチェックで複数当てはまった場合、必ずしも睡眠時無呼吸症候群と診断されるわけではありません。肥満や加齢、ストレス、生活習慣など他の要因によっても同じような症状は現れます。
重要なのは、「自分は安全だろう」と思い込まず、症状を見逃さないことです。
- ・ 朝の疲労感や日中の眠気が続く
- ・ 家族から呼吸停止を指摘される
- ・ 高血圧などの合併症をすでに持っている
このような場合は、専門医のいる呼吸器内科や耳鼻咽喉科、睡眠外来などで相談することを推奨します。
睡眠時無呼吸症候群の診断の流れと検査方法

睡眠時無呼吸症候群の診断は、問診・身体検査・睡眠検査を組み合わせて行われます。正確な診断のためには、専門的な検査が不可欠です。
1. 問診と生活習慣の確認
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、最初に行われるのは問診です。症状の有無や生活習慣、家族からの指摘などを医師が丁寧に確認します。特に以下の情報は重要な手がかりになります。
- ・ いびきの有無や頻度
- ・ 昼間の眠気や集中力の低下
- ・ 起床時の疲労感や頭痛
- ・ 高血圧や糖尿病など合併症の有無
- ・ 体格(BMI)、首回りの太さ、飲酒・喫煙習慣
これらの情報をもとに、医師は「睡眠時無呼吸症候群の可能性がどの程度あるか」を評価します。
2. 在宅で行える簡易検査
次のステップとして多く利用されるのが、携帯型装置を使った簡易検査です。手や鼻に小型のセンサーを装着し、睡眠中の呼吸状態や酸素濃度を測定します。自宅で一晩寝るだけでデータが得られるため、患者さんの負担が少なく、初期スクリーニングに適しています。
簡易検査では主に以下を測定します。
- ・ 無呼吸や低呼吸の回数
- ・ 酸素飽和度の低下度合い
- ・ いびきの有無
この検査で一定以上の異常が見られた場合、より精密な検査へと進みます
3. ポリソムノグラフィー検査(PSG)
睡眠時無呼吸症候群の確定診断に用いられるのが、ポリソムノグラフィー(PSG)です。これは医療機関で一晩泊まり、脳波・眼球運動・心電図・呼吸・血中酸素濃度・筋電図などを同時に測定する方法です。
PSG によって、無呼吸・低呼吸の回数や睡眠の深さ、心拍や酸素状態まで総合的に評価できるため、重症度の判定に必要不可欠です。
| 重症度 | 無呼吸低呼吸指数 (AHI:1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数) |
| 正常 | 5未満 |
| 軽症 | 5以上15未満 |
| 中等症 | 15以上30未満 |
| 重症 | 30以上 |
このAHIの数値を基準に、治療方針を決定します。
4. 診断は医師による総合判
セルフチェックや簡易検査で睡眠時無呼吸症候群が疑われても、診断は必ず医師による総合判断が必要です。症状の程度や合併症の有無、生活背景を含めて評価し、必要に応じて治療へつなげます。
睡眠時無呼吸症候群の治療法と改善へのアプローチ
睡眠時無呼吸症候群の治療は、重症度や病型、患者の状態に応じて選択されます。主な治療法には以下があります。
CPAP(持続陽圧呼吸)療法
睡眠時無呼吸症候群の中等症~重症に対して標準的な治療法として最も広く行われているのがCPAP療法(Continuous Positive Airway Pressure)です。就寝時に鼻に装着したマスクから一定の圧力で空気を送り込み、気道を広げて呼吸の停止を防ぐ方法です。
CPAPは中等症から重症の患者に有効とされ、夜間の無呼吸を減らすことで日中の眠気や疲労感の改善が期待できます。ただし、機器の装着に慣れる必要があり、継続して使えるかかどうかが効果に大きく影響します。
マウスピース(口腔内装置)療法
軽症例や、軽症例やCPAP が合わない場合に用いられるのがマウスピース治療です。就寝時に装着し、下あごを前方に固定することで気道を広げ、呼吸のしやすさを確保します。
歯科で作製されることが多く、持ち運びが簡単で旅行や出張時にも使いやすいのが特徴です。
ただし、顎関節症のリスクや歯並びへの影響が懸念されるため、医師や歯科医師の判断のもとで使用しましょう。
生活習慣の改善
治療とあわせて重要なのが生活習慣の改善です。軽症の方ではこれだけで症状が改善されることもあります。
| 減量 | 体重を減らすことで気道周囲の脂肪が減り、無呼吸の改善が期待できます。 |
|---|---|
| 飲酒制限 | アルコールは筋肉を緩め、気道閉塞を悪化させます。就寝前の飲酒は控えましょう。 |
| 禁煙 | 喫煙は気道の炎症を引き起こし、閉塞のリスクを高めます。 |
| 睡眠姿勢の工夫 | 仰向けで眠ると舌が喉に落ち込みやすくなるため、横向きの姿勢が推奨されることがあります。 |
これらは医学的治療と並行して取り組むことで、より良い結果につながります。
外科的治療
扁桃肥大や鼻閉塞など、明らかな解剖学的な原因がある場合には外科的手術が検討されることもあります。
例としては扁桃摘出術や鼻中隔矯正術などがあり、原因を取り除くことで気道の通りを改善する方法です。ただし、すべての患者に適応されるわけではなく、慎重な検討が必要です。
治療法選択の流れ
治療法の選択は、症状の重症度(AHI)・合併症の有無・生活習慣・本人の希望などを踏まえて医師が判断します。「これだけやれば必ず改善する」という万能な方法は存在せず、複数の治療を組み合わせることもあります。
重要なのは「症状を自覚したら放置せず、医療機関で相談すること」です。睡眠時無呼吸症候群は適切に対応すれば改善が見込める病気であり、生活の質や健康リスクを大きく変えることができます。
睡眠時無呼吸症候群を放置せず、早めに受診を

睡眠時無呼吸症候群は「気づきにくい」ことが特徴ですが、検査と治療を行うことで改善が期待できる病気です。
次のような症状が続く場合は、医療機関で相談することを推奨します。
- ・ 毎晩、大きないびきをかく/呼吸が止まっていると指摘される
- ・ 日中に強い眠気を感じ、生活や仕事に支障がある
- ・ 朝起きても疲れが取れず、頭痛や口の渇きが続く
- ・ 高血圧や糖尿病などの持病があり、症状が重なっている
特に家族から呼吸停止を指摘された場合は、見逃さず早めに医師へ相談することが大切です。
大切なのは「気になる症状を放置しない」ことです。症状が軽くても、長期的には体への負担となり、合併症のリスクを高めます。
治療により、あなた自身の健康はもちろん、ご家族の生活の質も大きく向上する可能性があります。一人で悩まず、医療の専門家とともに、より良い睡眠と健康な生活を取り戻しましょう。
睡眠は人生の約3 分の1 を占める重要な時間です。質の高い睡眠を確保することで、残りの3分の2の時間をより充実したものにすることができます。今日から、あなたの睡眠と健康について真剣に考えてみませんか。
(柊 こはる)
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠時無呼吸症候群」
[ https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/heart/yk-026 ] - 一般社団法人日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(SAS)診療ガイドライン」
[ https://www.jrs.or.jp/publication/file/guidelines_sas2020.pdf ] - 一般社団法人日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」
[ https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-05.html ] - 睡眠時無呼吸なおそう.com「睡眠時無呼吸症候群(SAS)現代病のリスク」
[ https://659naoso.com/sas/risk/ ] - 日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2019」
[ https://www.jds.or.jp/uploads/fckeditor/files/uid000025_474C323031395F77726974696E672D6F75746C696E652E706466.pdf ] - 一般社団法人日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」
[ https://www.jasso.or.jp/contents/magazine/journal.html ] - 自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策マニュアル【簡易版】
[ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/data/sas_manual_simple.pdf ] - 閉塞性睡眠時無呼吸症候群のリスク評価における日本語版STOP-Bangテストの有用性
[ https://www.jstage.jst.go.jp/article/generalist/42/1/42_26/_pdf ] - 日本語版 the Epworth Sleepiness Scale(JESS)~これまで使用されていた多くの「日本語版」との主な差異と改訂~
[ https://is.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/044110896j.pdf ] - 「いびき」が激しい、睡眠中「何度も呼吸が止まる」、日中の「耐え難い眠気」該当される方は要注意!栃木県警
[ https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n30/tetuzuki/ess.html ]